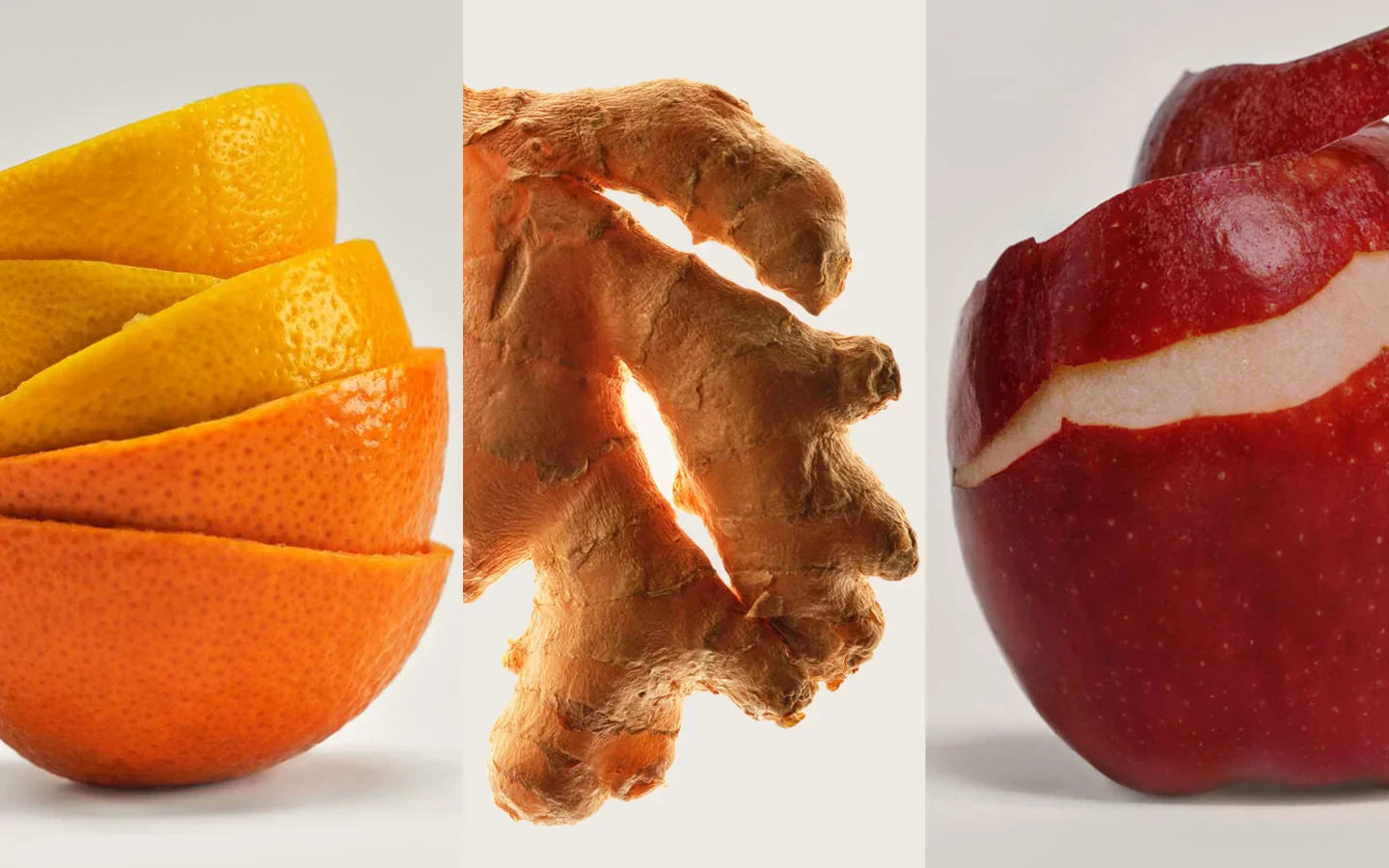アルカリ性食品で「バランス食」?知っておきたい基礎と効果

私たちの体には 酸とアルカリのバランス(=酸塩基平衡) を保つ仕組みがあります。
「アルカリ性食品」や「酸性食品」という言葉を聞いたことがあっても、実際にどう影響するのかよく分からない…という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、アルカリ性食品の基礎知識から、体への影響、具体的な食品リストまで分かりやすく解説します。
アルカリ性とは?仕組みを解説
私たちの血液は、常に pH7.35〜7.45 の範囲に保たれています。これはややアルカリ寄りの状態。
このバランスが崩れて pH が 7.35 を下回ると「酸性に傾いた状態(アシドーシス)」、逆に 7.45 を超えると「アルカローシス」と呼ばれます。
食事はこのバランスに影響を与えるとされており、「アルカリ性食品を多めにとることで体をサポートできる」という考え方が生まれました。
アルカリ性食品をとるメリット
アルカリ性食品を意識することは、結果的に 野菜や果物の摂取を増やすこと につながります。これらはビタミン、ミネラル、抗酸化物質を多く含み、体にさまざまなプラス作用をもたらします。
🍎 期待できるメリットの例
-
消化がスムーズになり、疲れにくくなる
-
骨や関節の健康をサポート
-
炎症を抑えるはたらき
-
肌の調子が整う可能性
もちろん効果の出方は人によって異なりますが、「酸性に偏りすぎない食生活」を意識すること自体が健康的だと言えます。
体への影響は?
アルカリ性食品を取り入れると、次のようなサポート効果が期待されます。
🌿 腎臓の働きを助けて老廃物の排出を促す
🌿 代謝の負担を軽くする
🌿 骨や軟骨への負担を減らす
こうした理由から、定期的に食事のバランスを見直し「アルカリ寄りの食品」を増やすのはおすすめです。
アルカリ性食品の例
「酸っぱい=酸性」というわけではありません。たとえばレモンやライムは酸っぱいけれど、体内ではアルカリ性に働きます。
🍴 主なアルカリ性食品
-
🥬 野菜:じゃがいも、ナス、ケール、サラダ類
-
🍊 果物:バナナ、オレンジ、ぶどう
-
🫐 ドライフルーツ:レーズン、いちじく、デーツ
-
🌿 ハーブ:パセリ、チャイブなど
-
🍵 飲み物:ハーブティー、ミネラルウォーター、コーヒー(適量)
手軽に取り入れられる食品が多く、無理なく続けられるのもポイントです。
酸性食品との違いを見極めるには
食品が体内で酸性かアルカリ性に働くかは「消化後の代謝」によって決まります。
⚖️ 主な分類
-
アルカリ性に働く:野菜、果物、ハーブ、芋類
-
中性に近い:玄米、油(オリーブ油・ひまわり油など)、アスパラガス
-
酸性に傾く:肉類、魚、チーズ、ソフトドリンク、アルコール、甘いお菓子
ひと目でわかるポイント
- ✅アルカリ性食品は、血液のpHバランスをサポートし、健康維持に役立つとされる。
- ✅野菜や果物を中心とした食事は、消化・骨・肌など幅広い健康効果が期待できる。
- ✅酸性食品とのバランスを意識しながら、アルカリ性食品を日常に取り入れるのがポイント。
アルカリ性食品で「バランス食」?知っておきたい基礎と効果

私たちの体には 酸とアルカリのバランス(=酸塩基平衡) を保つ仕組みがあります。
「アルカリ性食品」や「酸性食品」という言葉を聞いたことがあっても、実際にどう影響するのかよく分からない…という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、アルカリ性食品の基礎知識から、体への影響、具体的な食品リストまで分かりやすく解説します。
アルカリ性とは?仕組みを解説
私たちの血液は、常に pH7.35〜7.45 の範囲に保たれています。これはややアルカリ寄りの状態。
このバランスが崩れて pH が 7.35 を下回ると「酸性に傾いた状態(アシドーシス)」、逆に 7.45 を超えると「アルカローシス」と呼ばれます。
食事はこのバランスに影響を与えるとされており、「アルカリ性食品を多めにとることで体をサポートできる」という考え方が生まれました。
アルカリ性食品をとるメリット
アルカリ性食品を意識することは、結果的に 野菜や果物の摂取を増やすこと につながります。これらはビタミン、ミネラル、抗酸化物質を多く含み、体にさまざまなプラス作用をもたらします。
🍎 期待できるメリットの例
-
消化がスムーズになり、疲れにくくなる
-
骨や関節の健康をサポート
-
炎症を抑えるはたらき
-
肌の調子が整う可能性
もちろん効果の出方は人によって異なりますが、「酸性に偏りすぎない食生活」を意識すること自体が健康的だと言えます。
体への影響は?
アルカリ性食品を取り入れると、次のようなサポート効果が期待されます。
🌿 腎臓の働きを助けて老廃物の排出を促す
🌿 代謝の負担を軽くする
🌿 骨や軟骨への負担を減らす
こうした理由から、定期的に食事のバランスを見直し「アルカリ寄りの食品」を増やすのはおすすめです。
アルカリ性食品の例
「酸っぱい=酸性」というわけではありません。たとえばレモンやライムは酸っぱいけれど、体内ではアルカリ性に働きます。
🍴 主なアルカリ性食品
-
🥬 野菜:じゃがいも、ナス、ケール、サラダ類
-
🍊 果物:バナナ、オレンジ、ぶどう
-
🫐 ドライフルーツ:レーズン、いちじく、デーツ
-
🌿 ハーブ:パセリ、チャイブなど
-
🍵 飲み物:ハーブティー、ミネラルウォーター、コーヒー(適量)
手軽に取り入れられる食品が多く、無理なく続けられるのもポイントです。
酸性食品との違いを見極めるには
食品が体内で酸性かアルカリ性に働くかは「消化後の代謝」によって決まります。
⚖️ 主な分類
-
アルカリ性に働く:野菜、果物、ハーブ、芋類
-
中性に近い:玄米、油(オリーブ油・ひまわり油など)、アスパラガス
-
酸性に傾く:肉類、魚、チーズ、ソフトドリンク、アルコール、甘いお菓子
ひと目でわかるポイント
- ✅アルカリ性食品は、血液のpHバランスをサポートし、健康維持に役立つとされる。
- ✅野菜や果物を中心とした食事は、消化・骨・肌など幅広い健康効果が期待できる。
- ✅酸性食品とのバランスを意識しながら、アルカリ性食品を日常に取り入れるのがポイント。
アルカリ性食品で「バランス食」?知っておきたい基礎と効果

私たちの体には 酸とアルカリのバランス(=酸塩基平衡) を保つ仕組みがあります。
「アルカリ性食品」や「酸性食品」という言葉を聞いたことがあっても、実際にどう影響するのかよく分からない…という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、アルカリ性食品の基礎知識から、体への影響、具体的な食品リストまで分かりやすく解説します。
アルカリ性とは?仕組みを解説
私たちの血液は、常に pH7.35〜7.45 の範囲に保たれています。これはややアルカリ寄りの状態。
このバランスが崩れて pH が 7.35 を下回ると「酸性に傾いた状態(アシドーシス)」、逆に 7.45 を超えると「アルカローシス」と呼ばれます。
食事はこのバランスに影響を与えるとされており、「アルカリ性食品を多めにとることで体をサポートできる」という考え方が生まれました。
アルカリ性食品をとるメリット
アルカリ性食品を意識することは、結果的に 野菜や果物の摂取を増やすこと につながります。これらはビタミン、ミネラル、抗酸化物質を多く含み、体にさまざまなプラス作用をもたらします。
🍎 期待できるメリットの例
-
消化がスムーズになり、疲れにくくなる
-
骨や関節の健康をサポート
-
炎症を抑えるはたらき
-
肌の調子が整う可能性
もちろん効果の出方は人によって異なりますが、「酸性に偏りすぎない食生活」を意識すること自体が健康的だと言えます。
体への影響は?
アルカリ性食品を取り入れると、次のようなサポート効果が期待されます。
🌿 腎臓の働きを助けて老廃物の排出を促す
🌿 代謝の負担を軽くする
🌿 骨や軟骨への負担を減らす
こうした理由から、定期的に食事のバランスを見直し「アルカリ寄りの食品」を増やすのはおすすめです。
アルカリ性食品の例
「酸っぱい=酸性」というわけではありません。たとえばレモンやライムは酸っぱいけれど、体内ではアルカリ性に働きます。
🍴 主なアルカリ性食品
-
🥬 野菜:じゃがいも、ナス、ケール、サラダ類
-
🍊 果物:バナナ、オレンジ、ぶどう
-
🫐 ドライフルーツ:レーズン、いちじく、デーツ
-
🌿 ハーブ:パセリ、チャイブなど
-
🍵 飲み物:ハーブティー、ミネラルウォーター、コーヒー(適量)
手軽に取り入れられる食品が多く、無理なく続けられるのもポイントです。
酸性食品との違いを見極めるには
食品が体内で酸性かアルカリ性に働くかは「消化後の代謝」によって決まります。
⚖️ 主な分類
-
アルカリ性に働く:野菜、果物、ハーブ、芋類
-
中性に近い:玄米、油(オリーブ油・ひまわり油など)、アスパラガス
-
酸性に傾く:肉類、魚、チーズ、ソフトドリンク、アルコール、甘いお菓子
ひと目でわかるポイント
- ✅アルカリ性食品は、血液のpHバランスをサポートし、健康維持に役立つとされる。
- ✅野菜や果物を中心とした食事は、消化・骨・肌など幅広い健康効果が期待できる。
- ✅酸性食品とのバランスを意識しながら、アルカリ性食品を日常に取り入れるのがポイント。